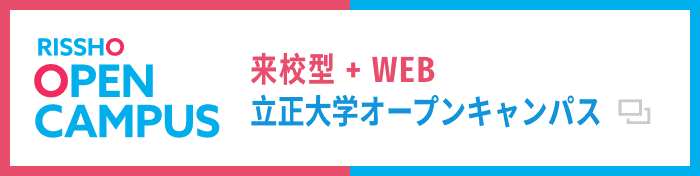- 子ども教育福祉学科
- 教育
- 研究
子ども教育福祉学科 リレーエッセイ(第4回)
チーム子福教員リレーエッセイの第4回目は、本年度子ども教育福祉学科の主任を務めています奥富が担当させていただきます。幼児の運動遊び、子どもの心身の健康課題などを専門としています。

暑い夏でも全身を使って遊ぶことのできる環境づくりを
奥富庸一(子ども教育福祉学科)
大学のある熊谷市は暑いことで全国的に有名ですが、いまや日本全国で熱中症警戒アラートが出されており、2024年度の日本の平均気温は1898年の統計開始以降、最も高い気温が更新されています(気象庁:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html)。
乳幼児は、体温調節機能は未熟とされており、また身長が大人と比べて低いことから、地面からの輻射熱の影響もあり、熱中症リスクの高い存在であることがいわれています。そのため、熱中症警戒アラートが発令されると、保育所や幼稚園、認定こども園等では外遊びを中止し、室内遊びに切り替えるなどの工夫をされています。その努力もあってか、令和5年度の7歳未満の乳幼児の熱中症による救急搬送は、全体の0.87%(救急搬送人員計91,467人のうち生後28日以上満7歳未満の乳幼児796人:令和5年5月~9月の間)でした。熱中症の危険は防ぐことができているといえますが、一方で、子どもたちの身体活動量は少なくなり、豊かな成長に必要な運動や全身を使った遊びがなかなかできない状況にもあります。暑い夏でももっともっと全身を使って遊ぶことのできる方法や環境を我々は考えていかなければと思います。
学生と教員が同じ視点で遊びの空間づくりを

夏に限らずですが、子どもたちが全身を使って遊べる場づくりと学生の体験の場づくりを兼ねて、奥富ゼミの学生を中心に子どもたちの遊びの広場「ハグくま広場」を行っています。空調の効いた室内ホールで、跳び箱や平均台、トランポリンやボールプールなどでつくられたサーキットコースで自由に遊べる空間をつくり、リズム体操やパラバルーンを使った運動遊びのプログラムをつくっています。学生と教員が同じ主催者側となって、子どもたちに遊びの空間をつくっていくことは、実習とはまた異なる視点での学生教育にもつながり、楽しさの中に大きな学びを得られる機会でもあります。
体験による学びを大切に

まつたけ幼稚園(行田市)での体力測定会
奥富ゼミでは、近隣の園にご協力いただき、調査や実践を通して卒業論文のテーマに取り組むこともあります。「ハグくま広場」しかり、体験による学びを大切に考えていますので、たくさんの子どもたちと関わるゼミになっていけばいいなと思っています。