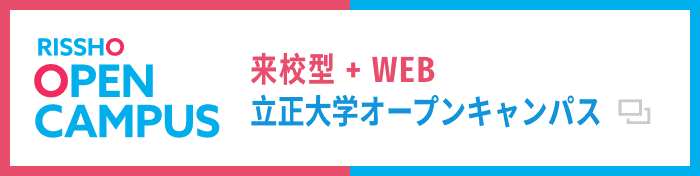- 子ども教育福祉学科
- 教育
- 研究
子ども教育福祉学科 リレーエッセイ(第3回)
子ども教育福祉学科教員リレーエッセイの第3回は、自然環境をテーマにした保育や幼児の人間関係に関するご研究をされている加藤直子先生です。授業は保育者論をはじめ、幼稚園実習や施設実習の担当をしています。保育・幼児教育に関する幅広い知識と経験で丁寧で細やかな実習指導をされる心強い先生です!

「子どもって、保育って面白い!」
加藤直子(子ども教育福祉学科)
「チーム子福」の加藤です。担当科目は、保育者論、幼稚園実習、保育所実習(施設)です。私が、幼稚園教諭、保育士を目指す学生に常に伝えていることは「子どもって、保育って面白い!」ということです。
「子どもって面白い」
幼稚園教諭や保育士の役割は、子どもたちの「生きる力」の土台を育むこと、言い換えれば、子どもがぐんぐんと伸びていくための“根っこ”を育てることにあります。それは、遊びを通しての総合的な指導によって実現されていきます。子どもたちは園に集い、集団生活の中で遊びながら関わり合い、ときにはぶつかり合ったり、笑い合ったりしながら成長していきます。そして、「どうすれば友だちと一緒に遊べるか」「もっと楽しくなるにはどうしたらいいか」を、自分の力で見つけていくのです。そんな子どもたちの姿を間近で見ていると、「えっ、そんなことするの?」「こんなこと考えてたの?」と驚かされる場面によく出会います。そういう瞬間に、改めて「子どもって本当に面白い!」と実感するのです。
「保育って面白い」
先日、イタリア北部のレッジョ・エミリアという小さな町に行く機会がありました。石畳の道が続き、100年以上前に建てられた建物が立ち並ぶその町は、まるで昔話に出てきそうな場所です。そんな場所で行われている教育は、「レッジョ・エミリア・アプローチ」として世界中から注目されています。特に幼児教育においては、子どもの主体性を大切にし、アート活動を通して自己表現したり、プロジェクト活動を通して友達と協働したりすることが重視されています。

保育者は、子どもたちの活動を側面から支え、その内面を理解するために、写真付きの記録「ドキュメンテーション」を作成します。これにより、子どもの育ちの軌跡が可視化され、保育者同士や家庭と子どもの成長を共有することができます。

世界中から高く評価されているレッジョ・エミリア・アプローチですが、実際に体験してみると、日本の保育との共通点が非常に多いことに気づきました。そして、日本でもまだまだできることがあると感じたのです。
保育は、子どもの姿から作り上げていくもの、面白い子どもたちの姿をきっかけに、その在り方を見つめ直していきます。「保育ってやっぱり面白い!」ですね。


写真 保育所のエントランスに貼られたドキュメンテーション
※ドキュメンテーションとは、保育中の子どもたちの様子を写真や動画などで記録する方法です。子どもの学びの過程を視覚的に記録することができ、これからの保育に生かしたり、保育者同士あるいは利用者(保護者)とのコミュニケーションの素材に使われるなど、近年注目されている手法のひとつです。