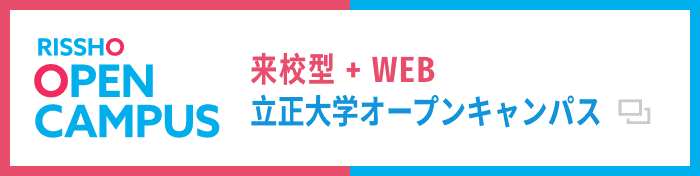大学院社会福祉学研究科

社会福祉学研究科長挨拶
立正大学大学院社会福祉学研究科が基盤とする社会福祉学や教育学は、人間のLIFE(生活/人生/生命)と社会に直接的にかかわり、そこに希望を託しながら探求を進める学問領域です。本研究科では、そうした土台の上で現代的な課題に取り組む研究を積み上げようとする研究者・実践者の養成に力を入れています。なかでも、福祉・教育・医療・保健などの分野で現に活躍されている方々が実践を省察し、それぞれのフィールドに還元する研究を展開することを後押ししたいと考えています。

各分野で仕事を継続する社会人を大事にしたいという観点から、授業は平日18時10分より開講するとともにオンライン受講が可能です。また、福祉系大学院の首都圏ネットワーク団体である社会福祉専攻課程協議会(現在12大学院)にも加盟し、他の大学院での講義も受講し修了単位に組み込むことができます。
大学院という空間での研鑽とそこからひろがるネットワークは、何より自分自身のLIFEを豊かにするでしょう。努力が研究成果として実り、社会に貢献できる喜びもかけがえがありません。多くのみなさんがこのプロセスに参画してくださることを期待しています。
教育・研究の特色
社会福祉学研究科では、福祉に関する高度で幅広い専門知識と技術、能力を身につけることができます。現代社会の構造や特徴を理解し、人間とその生活や発達を本質的に捉える広い視野、そして共感する心を有する豊かな人間性(福祉マインド)、近未来へのパースペクティブとを併せ持った人材を養成します。
「理論と実践の統合化」を教育目標に捉え、体系的に社会福祉学研究の知識の深化を図るとともに、実践的活動とのつながりを強化した教育に力を入れています。
カリキュラムと研究指導
修士課程は2年間でゼミナール群8単位、「基礎領域群」「社会福祉領域群」「教育福祉領域群」からなる研究特論群から22単位以上(必修科目含む・1科目2単位)を履修した上で、修士論文を作成します。各自の研究テーマと研究計画に基づいて、ゼミナール群を担当する教員の中から指導教員1名を届け出て決定します。
博士後期課程では、「研究指導(1~3年次・通年開講)」を核に、「社会福祉領域」「教育福祉領域」の特殊講義のうち12単位以上を履修するとともに博士論文の作成に取り組みます。研究指導は主任指導教員(主査)が行い、副指導教員(副査)が連携して進めます。博士論文が受理された者に対し「博士(社会福祉学)」の学位が授与されます。
授業時間とオンライン受講
立正大学大学院社会福祉学研究科は昼夜開講制の大学院ですが、原則として授業は平日以下の時間帯に105分授業として行われます。
| 大学院1限 | 18:10~19:55 |
|---|---|
| 大学院2限 | 20:00~21:45 |
原則全ての授業は国内のどこからでもオンライン受講が可能です。ただし、年度当初のガイダンス、修士(博士)論文中間報告会(年2回)、修士(博士)最終論文報告会などについては対面参加が必須となり、入学後一度もキャンパスに訪れることなく修了することはできません。また、授業によっては演習・実習により対面参加授業回がある場合もあります。
就学制度と支援
長期履修制度を活用することで、修士課程では3~4年、博士後期課程では4~6年に修業年限を延長できますが、修士課程は2年、博士後期課程は3年分の学費で修了することができます (詳細については大学院学生募集要項をご覧ください)。
本制度を活用することで、社会人の方でも余裕を持った履修、論文執筆が可能です。
成績等の要件を満たした学内進学予定者(4年生)については大学院科目の先取履修が可能です。必要な単位を取得すれば、修士課程を1年間で修了することができます。なお、立正大学卒業生は、社会福祉学研究科進学にともなう入学金は免除となります。
立正大学石橋湛山記念基金に基づく奨学金です。返還の義務はありません。
成績優秀者1名に対し年間50万円
(※2位者に対しては年間24万円 2026年度実績)
立正大学石橋湛山記念基金に基づく奨学金です。返還の義務はありません。
立正大学校友会の在学生支援事業に基づく奨学金です。返還の義務はありません。
人物・学業ともに優れ、経済的に修学困難な学生に対し、奨学金が貸与されます。
この制度は、わが国の大学(大学院を含む)に在籍する私費外国人留学生で、「留学」の在留資格を有する者が申請できます。
私費外国人留学生で成績・人物がともに優れ、かつ留学生活を続けていくために経済的な援助を必要とする留学生が申請できます。