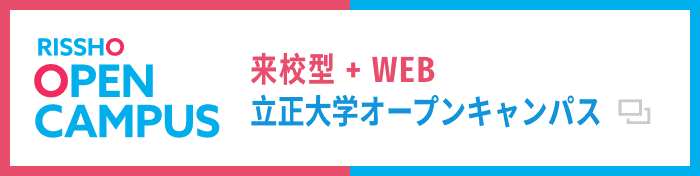- 子ども教育福祉学科
- 教育
- 研究
子ども教育福祉学科 リレーエッセイ(第1回)

2025年度、子ども教育福祉学科では、リレー形式で各教員の授業や研究の紹介を行うことになりました。第1回は、保育学や乳児保育、保育所実習等を担当しています志村聡子先生です。
「チーム子福」で学生支援!
志村聡子(子ども教育福祉学科)
子ども教育福祉学科(愛称は「子福」)では、子どもに関わる資格免許を取得できる養成課程を擁しています。保育士・幼稚園教諭・小学校教諭がその主な資格免許で、学生たちは進路希望に応じて、資格免許の取得を目指して学んでいます。養成課程は、多くの教員がチームとなって運営しています。言ってみれば「チーム子福」として、教員が互いに連携して学生の成長を見守っています。

歴史の視点で考える
私の研究分野は日本の教育の歴史です。担当の授業内では、折に触れて「歴史的背景」を取り上げています。例えば、日本に幼稚園ができたのは明治期、とか、近年認定こども園が導入された社会的背景、などです。現在の事項でも、その成り立ちの背景があることに着目してほしいのです。
子どもの意見する力を育てる
私の担当科目「保育学」では、子どもに関係する法律を取り上げています。最近では、こども基本法の制定(令和5年4月1日施行)が目新しいところであり、子どもに関心をもつ人は把握しておきたい法律です。同法制定の背景には、我が国で子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)について十分に配慮してこなかった反省があります。特に子どもの意見表明権(the right to express those views freely)を尊重することについて、関係者には熟考が求められています。原文の‘views’は日本語訳で「意見」ですが、大人に対峙して意見できる年齢が想定されているのではありません。乳児であってもその‘views’(その見えている世界、考え、意見)を尊重することが求められ、周囲の大人がそれらを読み取って代弁します。また、乳幼児期から子どもの意見を述べる力を育てるよう、「どうする?」「どっちにする?」などと、折に触れて丁寧に考えを聞く機会(子どもにとって、聞いてもらう機会)を設ける姿勢が大切です。
こども基本法の対象は「心身の発達の過程にある者」とされ、大学生も含まれます。本学科で学ぶ学生たち一人ひとりの、意見する機会を設けることに努めたいと考えています。

最後にひとこと
今後、「チーム子福」のメンバー(学科教員)によるリレーエッセイが続きます。お楽しみに。
(文献等)
山岸利次「乳幼児の権利を巡る今日的課題」『発達』第174号、ミネルヴァ書房、2023年5月。
喜多明人による問題提起(幼児教育史学会第19回大会シンポジウム「子どもの権利と保育・幼児教育―歴史と現状」2023年12月)。